契約形態にはいろいろとあります。
自分がどの契約で働いているのか知らない人も多いかと思いますが、実は契約によって責任や仕事の範疇が変わってきます。
特にプロジェクトマネージャーやフリーランスの方は知っておかないと痛い目にあうので覚えておきましょう。
請負契約
- 成果物(ソフトウェア)の完成を目的とする契約
- 完成した成果物に対して報酬が支払われる
- 請負業者は成果物の完成責任を負う
特徴
- 成果物の納品が完了しないと報酬が発生しない
- 業務の進め方は請負業者に任される
- 検収(完成したことの確認)が必須
メリット
受注側
- 明確な成果物ベースで報酬が得られるため、業務範囲が限定できる
- 自社で進め方を決めることができるので、新人などに経験を積ませることができる
- スケジュールや体制を自社で自由にコントロールできる
- 個人ではなく、会社としてノウハウや技術力を付けることができる
発注側
- 成果物に対する契約のため、支払う対価が明確(成果が出なければ支払い義務なし)
- 納期と成果物の品質が契約で保証される
- 基本的に予算は見積もりによって決まるので、発注側としては楽である
- 完成品の検収後に支払うため、リスクが比較的低い
デメリット
受注側
- 固定報酬型が多く、見積りミスや工数超過で赤字になる可能性
- 契約に無い作業を依頼されやすく、対応に苦慮することも
- スコープ外の変更要求に対し、追加仕様(費用)なのか都度交渉が必要
- 成果物の瑕疵(バグや仕様違反)について修正義務(無償)がある
※以前は納品から1年間でしたが法改正により、不具合を知ってから1年間に変更されました - 納期遅延や不完全な成果物により損害賠償請求される可能性あり
発注側
- 業務品質や進捗のコントロールが難しい
- ノウハウや技術が社内に蓄積しにくい
- セキュリティリスク(情報漏洩など)への配慮が必要
- 契約外の業務を依頼しにくく、柔軟性に欠けることもある
- 委託先の技術力に依存してしまう
個人的総評
きちんと見積や管理できる人がいる場合は利益になる上に、人材育成もできて一石二鳥にも三鳥にもなるため、どのソフトウェア会社も請負契約と取りたがるが、きちんと見積や管理できる人がいない(育ててない)ことが多く、請負=工数オーバー(残業)=予算オーバー(赤字)となっている会社がほとんどである。
きちんと見積や管理できる人いる場合は、利益も出して人材も育って、会社の環境もいい。
前提として、管理者(プロジェクトマネージャー)はプログラムを触らず、プロジェクトの管理に専念している必要があります。
入社しようか迷っている会社のときは面接の時に「管理者と開発は分業制ですか?」とずばり聞いてみるのも手かと思います。いろいろ言い訳して結局分業できていない会社は辞めたほうがいいでしょう。
労働者派遣契約
- 派遣会社が自社の社員(派遣社員)を他社に派遣し、その会社の指揮で働かせる契約。
- 労働者派遣法に基づき、厳格なルールがある。
特徴
- 派遣先が業務内容や勤務時間などを直接指示できる。
- 最大3年までの期間制限(例外あり)
メリット
受注側
- 人材を顧客企業に送り出すことで安定収益が見込める
- 自社でプロジェクトを持たなくても売上が立てられる
- エンジニアの稼働率を確保しやすい
- クライアントとの関係構築を通じて他の受託案件に繋がる可能性がある
- 報酬が成果物ではないため、請負契約のように品質を担保する必要がない
発注側
- 必要なスキルを持つ人材を短期間で確保できる
- 繁忙期など、業務量に応じて柔軟に人員調整が可能
- 社会保険や福利厚生などの間接コストを削減できる
- 正社員採用に比べて採用リスクが少ない
- 派遣契約終了時に比較的スムーズに契約解除できる
デメリット
受注側
- エンジニアが常駐先に依存しがちで、帰属意識が薄れやすい
- 優秀な人材ほど派遣先に引き抜かれるリスクがある
- 自社の技術資産やブランド構築がしにくい
- 派遣先の都合で契約が急に終了するリスクがある
- 派遣単価に限界があり、高収益化が難しい場合もある
発注側
- 業務指示や管理責任が発注側にある(直接指揮命令)
- 教育コストやノウハウの流出リスクがある
- 長期的なチーム形成やスキル定着が難しい
- 派遣法など法規制への対応が必要(期間制限など)
- 責任ある業務を任せにくく、業務範囲に制限がある
個人的総評
準委任契約(いわゆるSES)
- 「業務の遂行」を目的とする契約。労務提供に近い。
- 一定期間、技術者がクライアントの業務に従事する。
- 成果物の完成責任はない。
特徴
- 成果物がなくても、働いた分の報酬が支払われる。
- 作業時間(タイムチャージ)や稼働日に応じて課金。
- 常駐(オンサイト)型のSES契約などでよく用いられる。
メリット
受注者
- 作業時間に応じた報酬を得られるため、リスクが低い(成果物の完成責任がない)
- 要件変更に柔軟に対応しやすい(成果物の仕様確定が不要)
- 長期契約になりやすく、継続的な収益が見込める
- スキルやリソースの提供に集中できる(設計・開発・テストの一部など)
発注者
- 要件が固まっていなくても業務を進められる(アジャイル的な開発にも適している)
- 必要な期間・人数だけ人材を確保できる(柔軟なリソース調整が可能)
- 成果物の責任を持たせず、内部メンバーとして活用できる
- 社内の人的リソース不足を一時的に補える
デメリット
受注者
- 成果に対する報酬ではないため、高い付加価値を出しても単価が上がりにくい
- 契約更新がなければ即終了の可能性もあり、不安定
- スキルが合わないと現場での評価が低下しやすい(交代のリスク)
- 技術力よりも人月単価や稼働率で評価される傾向がある
発注者
- 成果物の完成責任は受注側にないため、進捗・品質管理を自社で行う必要がある
- 業務指示を直接行えない(指揮命令権がない)ため、管理が難しい
- 成果が出なくても時間分のコストがかかる(コスパが悪化する場合あり)
- 「偽装請負」のリスクがある(違法な形態になる可能性)
個人的総評
受注会社からすれば、安定的に収入が得られるので大きい。
作業管理者になればリーダーとしての経験を積むことができる。(ただし、偽装請負で本来必要な「SES企業側の責任者」がいないことが多い)
「SES企業側の責任者」から依頼された作業を行うだけでやりがいを感じにくい。
自分で提案したり挑戦がしにくい環境。また、常駐している場合は周りは他社の人間だったり自社の人間でもあまりコミュニケーションがないことが多く、スキルアップする機会が少ない。
そもそも偽装請負の可能性が高い。
偽装請負とは?
常駐先の人から直接作業指示を受けれるのは「SES企業側の責任者」となり、他のSESメンバーはこの「SES企業側の責任者」から作業指示を受けることになります。
もし、常駐先の人から作業指示を受けている場合は法律違反となります。
例外として、「SES企業側の責任者」は常駐先からの作業を行うことができます。
なら1人SESは?と思った方、するいどいです!「SES企業側の責任者」になりそうですが、法的にはアウトです。SESの場合は同じ現場に2名以上いる必要があります。ホント意味の分からない制度ですよね。
ちなみに、ほとんどが偽装請負ですが、バレれば、発注側・受注側ともに1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑となります。
業務委託契約
- 「請負」や「準委任」などを含む総称的な用語
- 内容によって実態が変わるため、契約書の中身が重要
特徴
- ベンダーやフリーランスとの取引で多用される
- 実態が「準委任」なのに「請負」と記載されていることも
メリット
受注者
- 必要な期間・スキルに応じて人材を確保できる
- 自社で正社員を雇うより人件費や福利厚生費を抑えられる
- 社内リソースが不足していても開発を進められる
- 専門性の高い技術者を外部から確保できる
- プロジェクト単位で契約しやすく、柔軟なリソース調整が可能
発注者
- スキルや経験を活かして柔軟に案件を選べる
- 成果報酬型であれば単価交渉の余地がある
- フルタイム雇用に比べて自由度が高い働き方ができる
- 同時に複数のクライアントと契約できる可能性がある
- 評価や実績によって継続的な受注に繋がることもある
デメリット
受注者
- 成果物が契約通りに納品されないリスクがある
- 業務の進捗や品質の管理に工数がかかる
- 機密情報の管理・漏洩リスクがある
- 長期にわたるとコストが割高になる場合もある
- 請負契約の場合、指揮命令ができないため柔軟な変更が難しい
発注者
- 収入が不安定になりやすい(案件ベース)
- 契約や納期、仕様変更などのトラブルリスクがある
- 業務指示は基本的に受けられず、自律的に進める必要がある
- 繁忙期と閑散期の差が大きくなることがある
- インフラや環境構築、管理コストを自分で負担する場合がある

会社員の方は、準委任契約・請負契約。フリーランスの方は請負契約・業務委託契約になるかと思います。契約により、責任範囲が異なったり、場合によっては違法行為になるので注意しましょう。
特にフリーランスの方は作業範囲を明確しないまま請負契約にしてしまうと、いつまで経っても完成せず、報酬がもらえなかったり、労働時間が見合わなかったりとトラブルになりがちです。業務委託契約の場合でもきちんと面接のときと作業内容が異なったりします。契約書の中身を読んでから契約するようにしましょう。
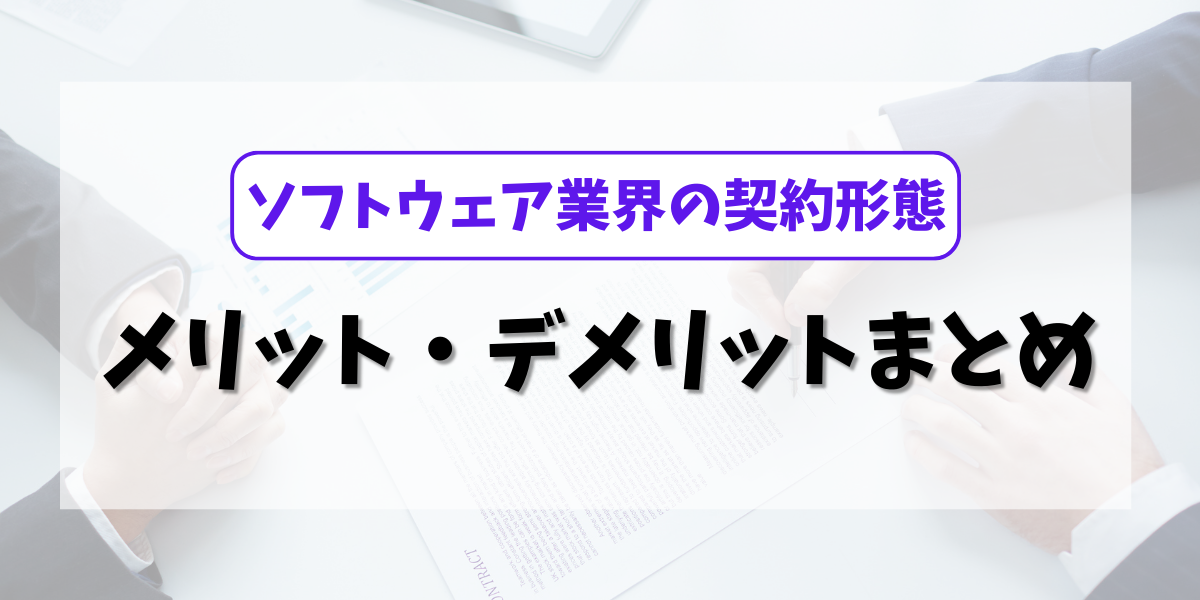
コメント